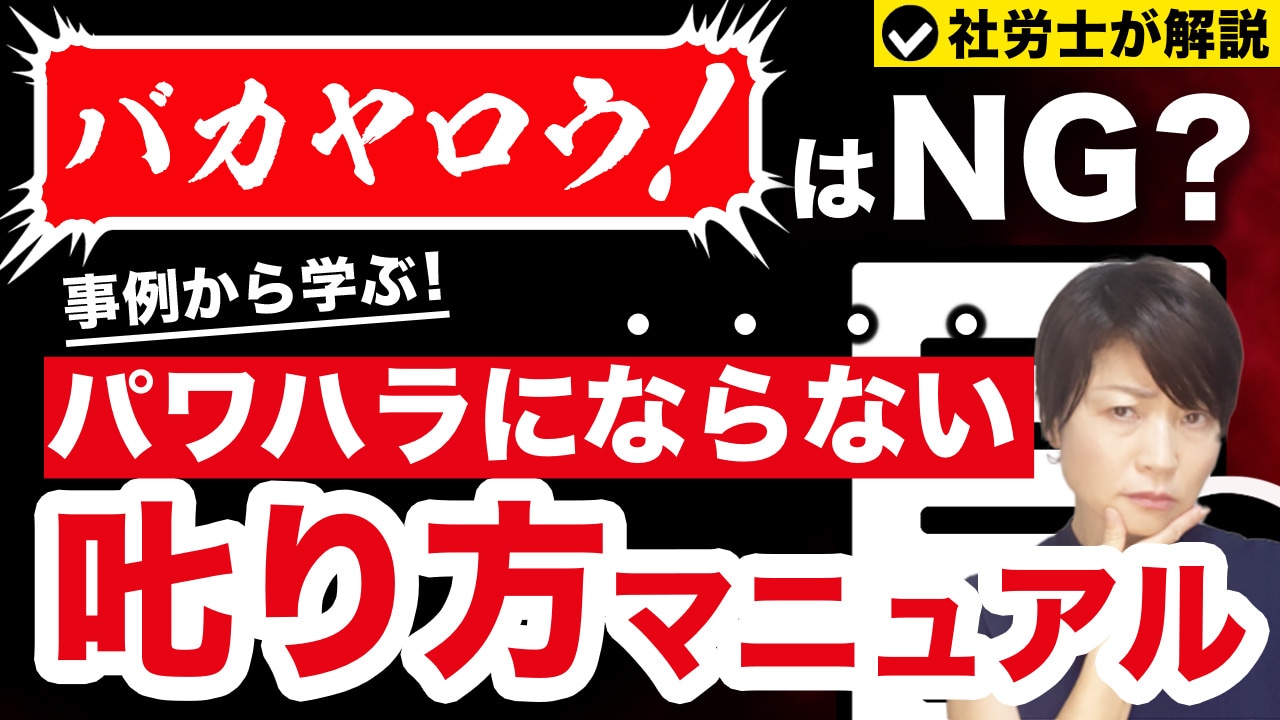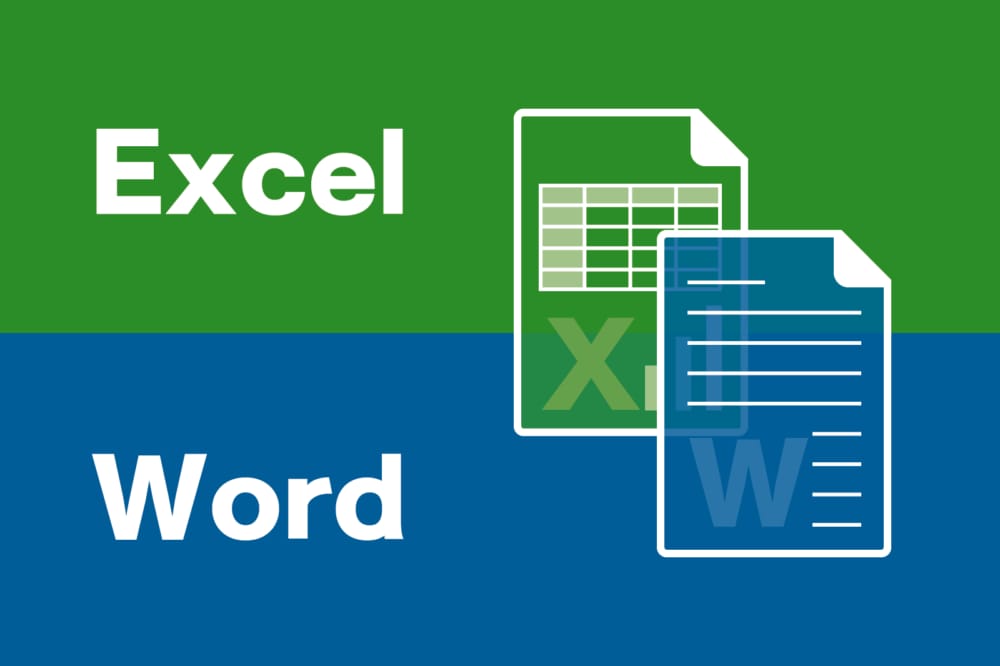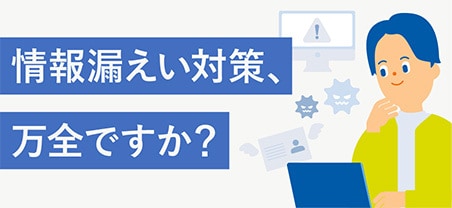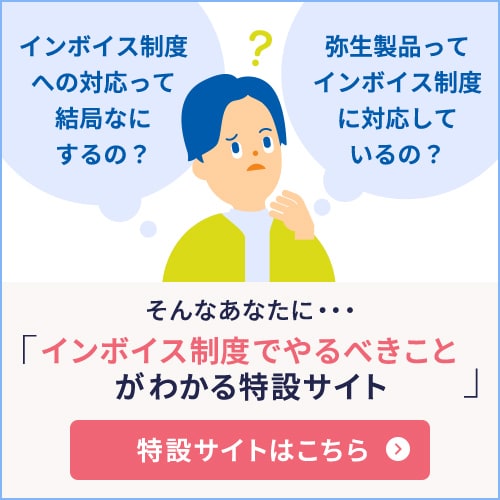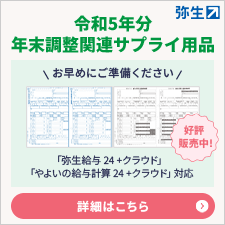- 経営ノウハウ&トレンド
どうすればいい?あなたの会社がネットで炎上したとき【風評被害の専門家に聞く】
2022.05.25
著者:金野和磨

自身に過失があるかどうかに関わらず、今や誰にでも発生しうるネット上での風評被害。「ユーザーからの不買運動」や「お得意先からの取引停止」をはじめ、あらゆる方面でネガティブな結果が起こりえます。
では、中小企業や個人事業主が風評被害や炎上に遭ってしまった場合はどんな対策を講じるべきなのでしょうか。ネット上の風評被害対策に強い弁護士として多数の実績を持ち、NHKのドラマ『デジタル・タトゥー』の原案も担当したモノリス法律事務所の代表弁護士、河瀬季(かわせ・とき)先生に伺いました。
[おすすめ] 確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」
目次
中小企業の場合、一度の炎上でほぼ売上がゼロになる可能性もある

──まずは河瀬先生のご来歴について教えてください。
河瀬先生(以下・河瀬):大学に進学してから26〜27歳までの間はWebサイトの制作を請け負うなど、IT関連の個人事業主として活動していました。その後は大学院で法律を勉強し、32歳で弁護士になりました。私はよく「ITに強い弁護士」と言われるのですが、実際は「弁護士資格を取ったIT屋」と言ったほうが正しいと思います(笑)。
私の事務所が提供している主なサービスは2つあり、具体的に言うと1つはシステム開発会社をはじめとしたIT企業の顧問弁護士。もう1つはITが苦手な企業に対してIT+法律の領域で行うサポートで、いわゆる「風評被害対策」もこれにあたります。
──河瀬先生が風評被害対策に取り組むことになったのはなぜなのでしょうか?
河瀬:風評被害対策に対応できる人間が少なかったからですね。風評被害に関する問題を解決するには、まず被害状況を正しく分析することをはじめとした、ITに関する知見が必要です。そして法律を使わなければ問題を解決できない場合もありますので、使うべき場合は法律を使う必要があります。つまり、ITと法律、この両方を駆使しなければなりません。私はもともとIT屋であり、同時に弁護士でもあるため、風評被害対策を専門領域としました。
──風評被害や炎上には、どのようなタイプのものがありますか?
河瀬:当事務所によく依頼が来るのは主に3つのタイプです。
1.営業・売上に影響を及ぼす風評被害
商品やサービスの悪評が流れて売上が下がってしまうケースです。たとえばバイトテロ(飲食店・小売店で働く非正規雇用の従業員が商品や什器を使用して悪ふざけする様子をSNSに投稿し、炎上すること)などが挙げられます。他には商品の欠陥に関する根も葉もない噂(商品に異物が混入していたなど)がSNS上で広まることもあります。
2.求人・採用に影響を及ぼす風評被害
「あの会社はブラック企業だから」など、職場環境や人間関係に関する悪評によって求人応募が減少するなどのケースです。数十年前までは求人の媒体といえばタウンページくらいでしたが、今ではほとんどがスマホやPCです。新卒の就活生や、転職したいと思っている人間は、ほぼ間違いなく就職・転職先として検討している会社の名前で検索しています。今やインターネットを使っていない求人が存在しないと言ってもいい状況だからこそ起こるケースです。
3.上場審査の障害になる風評障害
自社に関するインターネット上での悪評(「あの会社は違法行為をしている」など)が上場審査の障害になるケースです。たとえば新規の上場申請に伴って監査法人に上場審査のアドバイザーとして入ってもらうことがありますが、その監査法人からインターネット上での自社のレピュテーション(社会的評判・評価)に指摘が入った場合は、すみやかに対応しなければなりません。
個人事業主や中小企業は、インターネットを通じて売上や求人に悪影響があったのであれば「自社が風評被害に遭っている」と捉えていいと思います。
──炎上についてはどうでしょうか? 炎上によって売上が下がった事例などがあれば差し支えない範囲で教えてください。
河瀬:主力商品の種類が少なく、かつそれらをECサイト経由で販売している中小企業の場合、一度の炎上でその商品の売上がほぼゼロになる可能性はあるでしょう。今や多くの人が商品を購入する前にインターネットで検索しているので、検索エンジンのファーストビュー(検索結果画面で最初に表示される範囲)でマイナスな情報が書かれていたら購入率が下がる確率が高い。
たとえば全売上の50%を特定のECサイトに依存していて、炎上をきっかけにそのサイトの商品ページにネガティブな評価が30件ついたとしたら、その商品はまずまともに売れないでしょう。
自社名や商品名の検索結果の1ページめは定期的にチェックすべき

──中小企業や個人事業主自身がそうした風評被害や炎上にさらされていることを早期に発見するために必要なことは何でしょうか?
河瀬:一般論を語るのはなかなか難しいですが、会社名や商品名を検索サイトで検索してみて、その結果の1ページめは定期的に見たほうがいいと思います。また、売上や求人を特定のサイトに依存しているのであれば、そのサイト内の自社に関するページのコメント欄は監視すべきです。
また求人についての話としては、いま転職系の口コミサイトには主要なサイトがいくつかありますよね。「このなかで、どのサイトをチェックしておくことが一番大事ですか?」と聞かれることがあります。
これについては、自分の会社名で検索した時に最初に表示される転職サイトが会社によって異なるので、答えはケースバイケースです。あくまでも自分の会社名で検索した場合に最上位に表示される転職サイトでの対応を考えることが重要です。
──そもそも炎上や風評被害を生まないために注意しておくべきこと、準備しておきたいことは何でしょうか?
河瀬:中小企業や個人事業主の場合、オフラインでの人間関係のこじれがオンラインに出てしまうパターンが多いので、退職する従業員やお客さまへの対応に気をつけることがまず重要です。
2ちゃんねる(現5ちゃんねる)やまとめサイト等において生み出される炎上は、「数人いればつくれてしまう」ということを知っておいたほうがいいかもしれません。炎上はひとりでつくり出すことは難しいですが、3人いれば簡単につくれてしまいます。特に中小企業の場合、犯人は特定少数と考えても差し支えありません。まとめサイトなどで生み出される炎上は、不特定多数が批判しているように見えて、実はIPアドレスから発信者をたどると投稿元が3人くらいしかいなかった、なんてケースはあります。
──中小企業や個人事業主の場合、そうした問題の対策をするほどお金の余裕がなかったり、顧問弁護士がいなかったりする場合も多いと思います。対策マニュアルの整備や、いざ炎上した場合の連絡ルートの確立など、中小企業や個人事業主でもできる事前準備はありますでしょうか?
河瀬:たとえばECサイトを運営している企業がお客様対応マニュアルを整備するとか、自社でメディアを運営する場合に不用意な炎上をしないために記事作成マニュアルを整備するなど、炎上の火種が発生しないようにするための業務マニュアルは必要だと思います。
ただし、実際にインシデント(炎上や事故をはじめとした自社の驚異に繋がりかねない出来事)が発生した際の対応マニュアルまでは不要です。むしろインシデントが発生した時にマニュアルで対応していいのは大企業だけで、中小企業や個人事業主の場合、基本的には経営者や事業主がすみやかに判断して動くべきだと思います。
書き込みが「事実」か「感想」かによって削除の可否が決まる

──間違ったアクションを取ることで炎上を悪化させてしまうケースも散見されます。炎上や風評被害があったとき、してはならない対応はありますか?
河瀬:法的にも論理的にも筋の通っていないような削除請求を「上から目線」でしないようにすることでしょうか。「炎上は下手な対応すると再炎上する」という話をよく聞きますが、月に100〜200件の風評ページ(風評被害の元となっているインターネット上のページ)を削除している私の個人的な感覚として、風評ページの削除請求を行って再炎上したケースは、ほぼありません。
ちなみに、当事務所が炎上の原因となった書き込みなどの削除請求を行う場合、請求先の人間が過去に削除請求を受けたことをネット上で晒したかどうかは必ず確認しています。
また、ご自身でネットに反論する場合でも、筋さえ通っていればそうそう再炎上はしません。炎上するだけの原因が自社にあるのであれば謝るほかないですが、筋が通っていると判断するのであれば泣き寝入りする必要はないと思います。その反論に筋が通っているのかどうかの判断については弁護士やIT業者をはじめとした外部コンサルを使うべきだと思います。
売上や求人に支障がないと判断できれば、スルーすべし

──それほど深刻な状況ではないにも関わらず、余計なアクションをしてしまい、かえって炎上してしまうパターンもあると思います。無視・スルーした方がいい場合は、どのようなパターンでしょうか?
河瀬:中小企業や個人事業主の規模感で言うと、売上や求人に支障がないと判断するのであれば余計な反論はせず、無視した方がいいですね。
──例えば自社とは無関係の会社が炎上して、その会社名や商品名が自社と似ていることで炎上してしまった場合はどのように対処すればいいでしょうか?
仮に「株式会社A」という会社が死亡事故を起こしたとして、名前が自社とはそっくりではあるものの、実際は別の会社である「株式会社A」が誤解され炎上した……などの場合はいかがでしょうか。
河瀬:そう言う場合は予算を割いてマーケティングで解決するしかありません。そのような事態に陥った場合「株式会社A」と検索ボックスに打ち込むと「株式会社A 事故」「株式会社A 死亡」といったサジェストワード(※Googleなどの検索ボックスに検索キーワードを入力したとき、自動表示される検索候補キーワードのこと)が出てしまうことがありますが、そうした現象に対して法的にできることはありません。
なので「株式会社A」と検索ボックスに打ち込んだ際に別のワードがサジェストされるように対策するといったような、広報やマーケティングの力で解決する必要があります。
広報と風評被害対策は密接に関わっています。こうしたケースでは、法律ではなく広報の問題であると認識しなければ問題を解決できません。なので、なるべく全体像を見渡せる人間を近くに置いておいたほうが良いと思います。中小企業や個人事業主が、そういった事態になってしまった場合も同様ですが、経営者自らが対応することになるでしょう。
──風評被害を起こしている原因になっているWebページやSNSのページはどうすれば削除できるのでしょうか?
河瀬:一般論から言いますと、その書き込みの内容が嘘であれば削除申請をしやすいです。まずその書き込みが「事実」なのか、それとも個人の「感想」なのかを区別する必要があります。
事実に関してはそれが嘘であれば消しやすいですが、個人の感想(店員の対応が悪い、商品が美味しくないなど)については削除申請しにくいということですね。
ただし、飲食レビューサイトやSNSに関して言うと別の判断軸があります。たとえばその書き込みが「利用規約違反」ということなら削除申請できるのです。
飲食レビューサイトやTwitterなどのSNSは、自由な言論を形成することでプラットフォームとしての価値をつくっている会社であり、原則としてはユーザーからの投稿を消したくないと考えるはずです。ただし、自分たちで利用規約を決めている以上、それに反しているという主張であれば話が通しやすくなります。
各飲食レビューサイトもしっかりとした規約をつくっているので、いかにその投稿が規約に反しているかということを論証できればいいわけです。飲食レビューサイトの書き込みは消せないとおっしゃる方は多いですが、実際には簡単に消せるケースもあります。
──では、転職口コミサイトの投稿は消せるでしょうか?
河瀬:転職口コミサイトの場合は変化が目まぐるしいため、対応が一時的なものになりがちですし、あくまでも一般論としてですが、「消せる・消せない」の判断基準はその投稿が事実であり、具体的かどうかというところになります。ただし転職口コミサイトの場合も利用規約を定めているので、別途利用規約違反かどうかを検討することもできます。
問題を正しく認識し、全体の解決策の提案できる人間に依頼するべき
──中小企業や個人事業主が独力で対応する場合、風評ページを削除することができなかったり、風評ページの発信者を特定できなかったりすることも多いと思います。そういう場合はどうすればいいのでしょうか。
河瀬:まず、風評被害に対して弁護士にできる仕事は何かをご説明しましょう。1つは悪評の原因となった書き込みを削除するという仕事、もう1つは発信者を特定するという仕事の2種類があります。このうち「発信者の特定」については裁判所を使うしかありません。
風評ページが投稿されているプラットフォームを運営する会社から見た場合、顧客の個人情報を外部に提供することになります。そのため、情報提供しろと言われても原則としては無理なため、裁判所を通じた手続を行う必要があります。
──一般の企業や個人が「発信者の特定」をすることはできるのでしょうか?
河瀬:いえ、法律上、削除することも特定することもできません。裁判を広告代理店に委託することができないのと同じです。そういった交渉は「非弁行為」というもので、弁護士にしか対応できないのです。
──風評ページの削除にはどの程度の期間や費用を想定すればいいのでしょうか?
河瀬:これはケースバイケースですね。事務所によっても違うと思いますが、ある程度は定量的に言えます。裁判が不要な場合は1週間から2ヵ月、裁判所に申し立てる仮処分という手続きの場合は2〜3ヵ月ほどかかります。費用についてはページ削除がだいたい1ページ10万円、仮処分が50万円くらいと想定しておけば大きなズレはないと思います。
──では、Twitterで特定のツイートを削除したい場合は?
河瀬:ツイートは一過性のものなので、Twitterでツイートの削除を要する場合は少ないです。よほど自社に対して粘着的に攻撃し続けるアカウントがあった場合は発信者を特定するとか、アカウントの成りすましのような悪質なケースに対応することはありますが。
個人でもできることで言えば、利用規約違反の報告を定期的にするということですね。仮処分をするよりもコストパフォーマンスが良いです。

ただ、誤解のないように言っておくと、我々弁護士は説得的に論証することを専門としている以上、利用規約違反の申請をする専門家でもあります。なので、自社でもできることと全く同じことを弁護士がお金もらってやるということではありません。
自社内でさんざん利用規約違反の申請をしても消えないとされていた投稿も、弁護士を通すことであっさり消せたケースも多々ありますので。
──ちなみにモノリス法律事務所に依頼する場合、どのような手続きを経ての依頼になりますか。また、依頼にあたり依頼元が準備しておくべきものや情報はありますか。
河瀬:当事務所に関して言えば、会社名・商品名や解決したい事柄をメールか電話で教えていただければ、発生している問題やその対策を分析して提案します、という流れですね。あとはインターネットで検索してもわからない情報(商品名など)があれば教えてほしいです。
基本的には会社名を聞いただけで無料診断から全体の解決策の提案までをつくることはできるのですが、公表されていない情報については把握ができませんので。
会社名だけ教えていただければインターネット上の問題はリストアップしますし、解決すべき優先順位に基づいてプランA・B・Cまでつくります。それにフィードバックをいただければ、それに応じてプランを組み替えます。そういう意味で当事務所は、法律的な業務にも対応するITコンサルと称したほうが正確かもしれません。
弁護士は職人と言われることがよくありますが、それにはいい意味と同時に悪い意味もあると思っています。職人は言われたことはしっかりとこなす一方、問題の根本原因や本質には目を向けない傾向があります。会社が弁護士に求めていることに、それでは応えきれないのではないかと思います。
──ITコンサル的な領域まで対応できる法律事務所って他にあるのでしょうか?
河瀬:あまりないと思います。我々は他の弁護士がライバルだとは思っていないですし、法的に私では対処できないことがあれば先輩弁護士をクライアントに紹介しようとも思っていますので。私の事務所の場合、問題解決の上流から対応できるという意味で、インターネット広告代理店のような会社が競合なのではないかなと思っています。
──本日はどうもありがとうございました。

河瀬季かわせ・とき
1981年生まれ。モノリス法律事務所代表弁護士。JAPAN MENSA会員。
大学の工学部に進学後はフリーランスのITエンジニア・ライター業務や、IT企業経営を経て、東京大学大学院法学政治学研究科に入学し弁護士に転身。ネット上の風評被害対策に強い弁護士として知られ、NHKのドラマ『デジタル・タトゥー』の原案も担当した。
・モノリス法律事務所
photo:塙薫子

この記事の著者
金野和磨
人材派遣会社、音楽サービス会社の営業職を経験した後に編集者・ライターとして活動を開始。2015年にはミュージシャンのプロモーションをサポートする会社、Gerbera Music Agency合同会社を設立。分かりやすい記事を書くことを心がけています。
資金調達ナビ
弥報Onlineでは「読者の声」を募集しています!
弥報Online編集部では、皆さまにより役立つ情報をお届けしたいという想いから「読者の声」を募集しております。
「こんな記事が読みたい!」「もっと役立つ情報がほしい!」など、ご意見・ご感想をお聞かせください。
皆さまからのご意見・ご感想は今後、弥報Onlineの改善や記事作りの参考にさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
弥生のYouTubeで会計や経営、起業が学べる!
関連記事
事業支援サービス
弥生が提供する「経営の困った」を解決するサービスです。