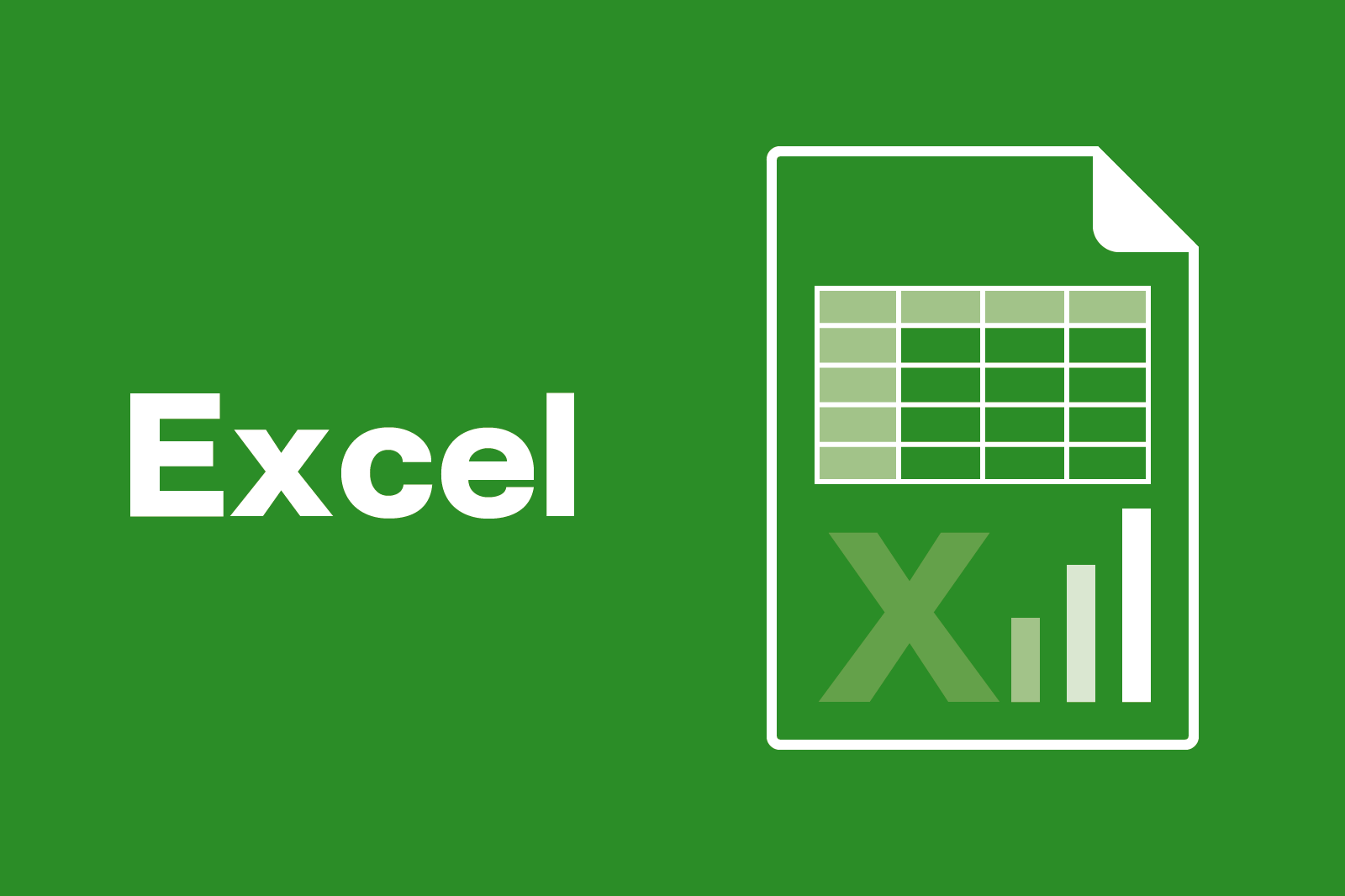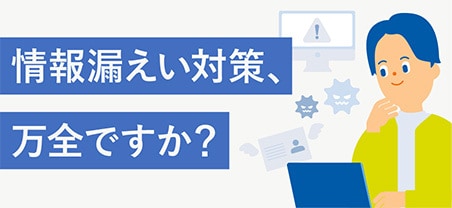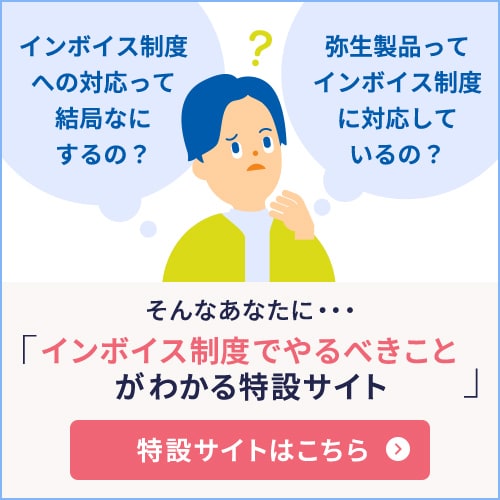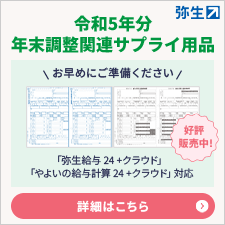- 経営ノウハウ&トレンド
個人事業主・会社経営者によくある相続の失敗談とその対応策
2022.05.26

個人や法人の事業経営者の後継者の方から相続の相談を受けることがよくあります。その内容は様々ですが、ほとんどの場合、手遅れの場合が多いです。生前の相続対策が手遅れで、経営者の方が事業承継の重要さに気づかなかった事が原因です。いわば余りにも事業に専念し過ぎていたために、相続対策を怠って多額の相続税を支払うことになってしまうのです。まずは、良くある失敗例でご自身の相続について考えてみましょう。
[おすすめ] 法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」
目次
後継者が従業員の信頼を勝ち取れていないケース
後継者であるべき長男は、「会社経営者に向いていない」と考え、父親の事業には全くタッチせず、会社員として働いてきた。しかし、父親の死去により、急きょ社長として父親の事業を引き継ぐこととなった。結果、父親と共に事業を大きくしてきた社員や取引先からの信頼を獲得できず、事業が立ち行かなくなるケース。
後継者が急に社長になって事業の成長が止まってしまうことが多々あります。多額の相続税がかかる以前の問題として、従業員や取引先の信頼を獲得することが、上手な事業承継の第一歩です。そういった後継者は、時として「自分には事業を承継する能力もないがどうしたらいいか…」と悩み、もがき苦しみ、結局事業に失敗してしまいがちです。
こうなってしまってからでは、大きく育てた事業を後継者の代で更に軌道に乗せ拡大していくことは難しくなります。また、許認可が必要な事業では、社長の業務経験が足らず許認可が下りないこともあります。
一旦、「従業員が一致団結するために、適した人は誰か」を考え、他人への事業承継も考えましょう。新しい経営者に資力がなければ株式の一部しか買取れないので、経営者としての地位が不安定になります。そこで、定款変更により代表取締役の任期を一定期間保障する手当てが必要になります。
株価が高額となってしまい、相続税が多額になるケース
父親は強いリーダーシップと独断で、戦後の日本経済の成長と共に事業を拡大してきた。いざ相続税対策を考えたところ、株価が高額になり多額の相続税が課税されてしまうケース。
上場していない企業であっても、事業の成長と共に株価が高額になることが多く発生します。親族で株式を保有していることで安心してしまい、株価対策を行っていないと、相続時に数十億円の株価になっているなんてこともよくある話です。
手立てを打っていないと、株主である親類一同から、今のうちに株式を買い取ってほしいと要求されても、個人で買取れるだけの預貯金を持っていないので対応ができないのです。
会社の経営者は、最低、3年に1回は自社株式の株価評価してください。株式評価するのに数十万払うのか、数億円の相続税を払うのか考えてみましょう。絶対に株式評価をしておいた方がトクなのです。そのうえで、株式の価額が上昇する前に売買や生前贈与などで処理してしまいます。買取り資金の確保のためには早くから解約返戻金の多い大口の生命保険に加入しておくことも方法の1つです。
せっかく大きくして来た事業だからこそ、空中分解する前に手を打っておく必要があるのではないでしょうか。
事業の承継者でもめるケース
次男は長い期間、父親と共に会社経営に従事してきた。父親の死去後、会社経営に全くタッチしていなかった長男も自社株式の一部を相続する。次男は業務を引継ぎ社長にはなったが、長男も会社の役員に就任し経営にあれこれ口出しするようになり、意見の相違が生じて今までよりも経営がスムーズに行かず、業績も悪化してしまうケース。
後継者として育てた子供と事業にタッチしていなかった子供がいる場合に起こりうる事例です。
相続では、正式な遺言書が無い場合、原則として相続人同士の話し合いで相続を行うこととなります。被相続人が、今まで一緒に事業をしてきた子供に事業を承継させたくても、被相続人が思うような相続が行われないことが多いのです。また、次男が事業を継いでいる場合も問題が起こることがあります。一昔前になら家督相続で長男がすべて引き継ぐ考え方もありました。その名残からか、長男が相続時に突如力を持つことも多々あるのです。
こういった場合に備え、生前に公正証書遺言や秘密証書遺言などで、自社株式の取得者を決めておく必要があります。
【まとめ】会社法でも対応できること
相続の失敗をしないためには、経営者が元気に活躍しているときに対策を考える必要があります。
例えば、会社法を利用した相続対策も1つの方法です。
- 定款に、「その株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨」定める
- 配当優先の議決権制限株式(無議決権株)を活用し経営者一族の支配権を高める
- 定款の規定によって、会社が所有する事業用財産と経営を分離できるようにしておくなどです。
相続は被相続人ごとに対応策がことなります。ぜひ、専門家に相談し、事業をうまく引き継ぎ、更なる事業成長できる対策を行っておきましょう。
photo:Thinkstock / Getty Images

この記事の著者
木村金藏
税理士。木村金藏税理士事務所所長。
5歳の時に父親が急死し孤立奮闘悪戦苦闘の連続で、「金蔵」の名前を汚さないよう「地主さんの財産を金の蔵に納める」仕事に専念。
上野で開業40年、法人や所得は勿論、他に相続、贈与、譲渡の申告の実績多い。資産を有効活用しながらの相続税対策の提案。どんな案件でも、資産税専門の資産税研究会で問題を提起し解決。
資金調達ナビ
弥報Onlineでは「読者の声」を募集しています!
弥報Online編集部では、皆さまにより役立つ情報をお届けしたいという想いから「読者の声」を募集しております。
「こんな記事が読みたい!」「もっと役立つ情報がほしい!」など、ご意見・ご感想をお聞かせください。
皆さまからのご意見・ご感想は今後、弥報Onlineの改善や記事作りの参考にさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
弥生のYouTubeで会計や経営、起業が学べる!
関連記事
事業支援サービス
弥生が提供する「経営の困った」を解決するサービスです。